PFIの基本スキーム~SPCを利用する意味と注意点~
通常、PFIにおいて、PFI事業のみを行うSPCを設立し、SPCと公共が事業契約を締結します。SPCはいわゆるペーパーカンパニーであり、SPCそれ自体はPFIを遂行する能力は有しません。
そこで、今回のコラムでは、PFIで構築されるスキームを紹介し、なぜそのようなスキームを構築するのか、スキームを見るうえでの注意点を中心に説明します。
1. 基本スキームと当事者
PFIにおいては、以下のスキームが採用されます。
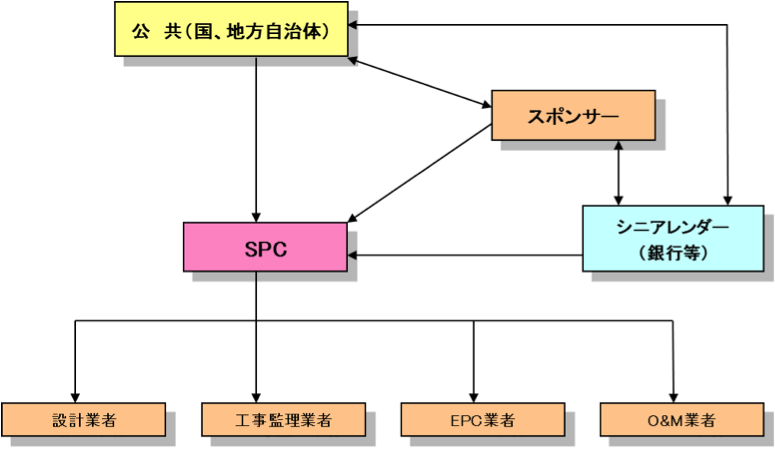
(当事者)
- 公共
- SPC
- 業務受託者
- シニアレンダー
・PFIの発注主体です。
・事業契約の当事者となります。
・公共と事業契約を締結する当事者となります。
・コンソーシアム(入札に参加した企業グループ)により設立されます。
・PFI事業のみを行う単一目的会社で、いわゆるペーパーカンパニーです。従業員もいません。
・コンソーシアムのメンバーです。
・SPCの株主(スポンサー)です(但し、コンソーシアムの全メンバーが株主になるとは限りません。)。
・SPCから、設計業務、建設業務、維持管理業務等を受託します。
・SPCに対して融資する金融機関です。シンジケーションを組成することもあります。
・プロジェクトファイナンスによる融資です。
これらの当事者の間で、事業関連契約、業務委託契約、融資関連契約、担保関連契約等の20本近くの契約が締結されてPFIが事業として運営されます。
→参考:コラム「PFI関連契約を理解するための3つのステップ」
2. SPCを設立する意味とメリット
なぜ、SPCを設立して複雑になるスキームを採用するのでしょうか。
ポイントは、SPCが他の当事者からは独立した一つの法人であることです。独立した存在であることにより、PFI事業を安定的に継続していくための以下のメリットが生じます。
- SPCはPFI以外の事業を行わないので、他事業の経営リスクがPFI事業に波及しない。
- SPCは別法人なので、コンソーシアムメンバーの経営リスクが波及しない。
- SPCは独立の単一目的会社なので、レンダーはキャッシュフローを管理しやすい。
SPCは、倒産隔離されており、資金調達もしやすくなるのです。
以上を前提に、各当事者にとって以下のメリットが生じます。
公共:コンソーシアムメンバーが倒産しても、PFI事業は遂行されることが期待できる。
コンソーシアムメンバー:PFI事業のリスクは、SPCを介して間接的に負担すれば足りる。
レンダー:PFI事業のキャッシュフローを分離でき、コントロールすることが可能になる。
3. スキームから生じる注意点
上記2.でSPCスキームとすることのメリットを説明しましたが、一方で、SPCであることから生じる注意点があります。
- SPCは、各種業務を履行するための資金も能力も独自に有していない。
- 事業契約上の義務はSPCが負っている。
このままでは、SPCは債務不履行に陥ってしまう。
![]()
そこで、SPCが負担する義務を、コンソーシアムメンバーに代わりに履行してもらう。
SPCスキームにおける最大の注意点は、業務委託契約において事業契約上のSPCの義務を完全に移転できているかです。
「移転できているか」には、事業契約上の各業務の履行義務だけではなく、費用やリスクの負担も含みます。
→参考:コラム「PFIにおける業務関連契約のポイント」
PFIにおいては、各事業により委託される業務、生じる費用・リスクは異なります。これらをスキーム上どのように分担していくか、その分担を契約書上適切に規定できているかがPFI事業の円滑な遂行を大きく左右します。
スキームを契約書によって上手く構築できているかは、事業契約上の義務の履行だけではなく、融資に関する契約にも影響します。スキームの構築に失敗すると、融資関連契約上のデフォルト(期限の利益の喪失)につながり、PFI事業の継続に大きな影響を与えてしまいます。
以上のとおり、PFIにおけるスキームがどのようなものであり、なぜSPCを利用するのか、スキーム自体からどのようなリスクが生じるのか、どのような措置をとる必要があるのかを理解することが、PFI事業を行う上で重要であり、かつ、とても有用です。
PPP/PFIチームでは、講演活動、研究会、質問会を行っています。PFIに関する基本事項から実務上のノウハウを習得して、PFIに積極的に参加の上、PFIを成功させましょう。
ご要望に合わせてプランニングしますので、以下の弁護士名をクリックいただき、お問い合わせフォームよりご連絡ください。











